昨年の春、近所の公園の通路脇にスギナが群生しているのを見つけました。
スギナとツクシは同じ地下茎から生えるから、次の春先に来ればツクシの群生が見られるはず。
昨日、同じ場所へ行ってみました。
ツクシの群生を見つけた

予想通り、たくさんのツクシが生えていました。
これだけの群生を見たのは久しぶりです。
ツクシが育ちやすい環境がなくなってきていますから、市街地でツクシの群生を見られる場所は貴重です。
公園の敷地内ですから、宅地として造成される心配はありません。
ただ不用意に整備されてしまわないかぎり、毎年観察できるでしょう。
ツクシの呼び名はスギナに付いて出てくることから「付く子」、茎の袴の部分で継いでいるように見えることから「継く子」になったようです。
漢字で書くと、土から出た筆のようだから土の筆と書いて土筆。分かりやすいですね。
同じ地下茎から役割の違う茎が出る
僕はスギナがツクシの成長形だと思っていたのですが、調べて見たら、スギナとツクシは役割が異なる別の茎ということでした。
ツクシは胞子茎

ツクシは3月の中旬頃に生える筆のような形をした茎です。
先にある穂のような部分から胞子を放出して生息域を拡大していきます。

上の画像はツクシの穂先を拡大したもの。
胞子が見えていますね。
たたくと白い粉が舞い散ります。
ツクシは食べられます
ツクシは春の山菜として、卵とじ、お浸しなどに料理して食されます。
スギナは栄養茎

スギナはツクシより遅い時期から生えてきます。
画像は昨年の4月8日に同じ場所で撮影したもの。
画像のようにスギの木の形に似ているからスギナと呼ばれます。
ツクシと違い、植物らしく緑色をしています。
植物の緑色は光合成をするための葉緑素を含んでいるためですが、スギナも光合成を行います。そのため栄養茎と呼ばれます。
まとめ
ツクシとスギナは同じ地下茎から生える同じ植物体ですが、ツクシは胞子を放出する繁殖の役割、スギナは自身が成長するために必要な養分を取るための役割を持っています。
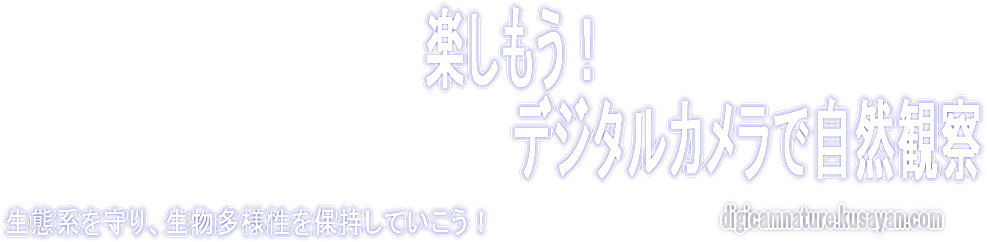




コメント