連日、最高気温が35℃を上回る日が続いてます。
こういう気候になると、撮影する人間自身も辛いですし、撮影される昆虫たちも日陰に身を隠したりしています。
意外に昆虫は暑いのが苦手だったりします。
真夏の昆虫撮影は気温が上がらない午前中がベストですね。
この時期の昆虫というと、トンボか蝉となりますが、蝉といっても関西ではアブラゼミ、クマゼミ、ツクツクボウシが定番。
関東以北の夏の定番であるミンミンゼミは山手の涼しい場所でしか鳴き声を聴くことができません。
緑に囲まれた公園を散策してみると、木の枝や葉に蝉の抜殻をたくさん見つけました。

蝶や蛾の仲間は幼虫期のイモムシ状から繭や蛹を経て、美しい羽根を持った成虫になります。これを完全変態と言います。
蝉やトンボなどは繭や蛹の形態を取らず、幼虫が脱皮してそのまま成虫になります。これを不完全変態と言います。
脱皮した抜殻はそのままの形を保ったままぶら下がっていますので、あちらこちらに抜殻を見つけることができます。
抜殻はきれいな形状を保ったままですので、撮影対象として美しい絵となります。
大切なのは構図で、どの位置に抜殻を置くか?背景をどうするか?です。
被写体をど真ん中に置く、日の丸構図より、やや下方に置き、手前に空間を持ってくる位置がベストだと思います。
上の「カエデ林のアブラゼミの抜殻 」の画像は被写体である抜殻がほぼ真ん中位置にあるので、もう少し下方にした方が良かったと思います。
下の画像「苔むした老木のアブラゼミの抜殻 」は抜殻の位置を下方にできているので、バランスも良く、いかにも木の上を目指して登る幼虫の行動をイメージすることができます。


本記事で掲載した画像はSONYα6500で撮影しています。
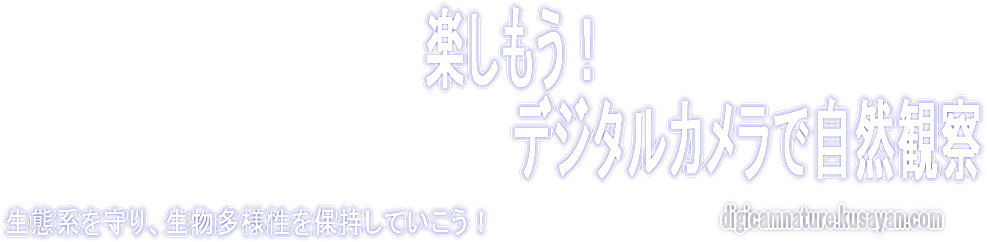




コメント