道端の花や家庭菜園で、ホバリングしながら蜜を吸う小さな昆虫を見かけたことはありませんか?もしかしたらそれは、私たちの生活に役立つ益虫「ホソヒラタアブ」かもしれません。一見するとハチのようにも見えますが、実はアブの仲間。今回は、この小さくてもパワフルなホソヒラタアブの知られざる特徴や生態について、詳しくご紹介します。この記事を読めば、きっとあなたもホソヒラタアブのファンになるはず!
ホソヒラタアブってどんな虫?~まずは基本情報から~

ホソヒラタアブ(学名:Sphaerophoria macrogaster)は、ハエ目ハナアブ科ヒラタアブ亜科に属する昆虫です。名前に「ホソ」と付く通り、他の多くのヒラタアブ類に比べて体つきが細長いのが特徴です。「ヒラタアブ」という名前は、幼虫が扁平な形をしていることに由来するとも、成虫が平たく止まる習性から来ているとも言われています。
【分類】
- 界:動物界 Animalia
- 門:節足動物門 Arthropoda
- 綱:昆虫綱 Insecta
- 目:ハエ目 Diptera
- 亜目:短角亜目 Brachycera
- 科:ハナアブ科 Syrphidae
- 亜科:ヒラタアブ亜科 Syrphinae
- 属:ホソヒラタアブ属 Sphaerophoria
- 種:ホソヒラタアブ S. macrogaster
日本全国の平地から山地まで広く分布しており、畑や水田、草地、公園、庭先など、比較的どこでも見かけることができる身近な存在です。成虫は主に春から秋にかけて見られ、特に春と秋に個体数が増える傾向があります。
見た目の特徴~ハチにそっくり?見分け方のポイント~

ホソヒラタアブの成虫の体長は7~10mmほど。細長い体と、黒地に黄色の縞模様が特徴的です。この模様がミツバチやアシナガバチなどのハチ類に似ているため、「ハチに擬態しているのではないか」と言われています。これは、捕食者から身を守るためのベイツ型擬態の一例と考えられています。しかし、よく見るとハチとの違いは明らかです。
【ホソヒラタアブとハチの見分け方】
| 特徴 | ホソヒラタアブ (ハエの仲間) | ハチの仲間 |
| 翅(はね) | 1対 (2枚) | 2対 (4枚) ※ただし、飛ぶときは連結して1対に見えることも |
| 触角 | 短く、目立たない | 長く、目立つものが多い |
| 複眼 | 非常に大きく、頭部の大部分を占める。オスでは左右の複眼が接する種が多い。 | 複眼は大きいが、ハエほどではない。 |
| 口器 | 舐める口 (花蜜などを舐めとる) | 噛む口、または舐める口と噛む口の両方を持つ |
| 針 | 持たない | メスは産卵管が変化した毒針を持つ種が多い |
| 飛び方 | ホバリング(空中停止)が得意 | 直線的に飛ぶことが多い |
特に、ホソヒラタアブは空中でピタッと静止する「ホバリング」が非常に得意です。これはハエ目の昆虫に共通する特徴の一つで、花の蜜を吸う際や、メスを探すオスが周囲を警戒する際などに見られます。
【ホソヒラタアブの詳しい形態】
- 頭部: 大きな複眼が特徴です。オスは左右の複眼が頭頂部で接しているか、わずかに離れているのに対し、メスは左右の複眼が完全に離れています。これにより、雌雄の判別が可能です。触角は短く、先端が少し太くなっています。
- 胸部: 黒色で光沢があり、種類によっては黄色の縦縞や斑紋が見られます。
- 腹部: 最も目立つ特徴で、黒色の地に鮮やかな黄色の帯状の斑紋があります。この斑紋のパターンは個体変異や、近縁種との識別に重要です。ホソヒラタアブの名前の通り、腹部は細長い棍棒状で、特にオスは腹端が丸く膨らんでいることが多いです。メスの腹部はオスに比べてやや太く、先端が尖っています。
- 脚: 黄色や黒色で、特に目立つ特徴はありませんが、しっかりと草木に掴まることができます。
- 翅: 透明で、中央付近に偽縁紋(ぎえんもん)と呼ばれる、翅脈が途切れたように見える部分があるのがハナアブ科の特徴の一つです。
ホソヒラタアブの生態~知られざる暮らしぶり~
ホソヒラタアブは、私たちの身近な環境でどのような生活を送っているのでしょうか。その生態は非常に興味深く、人間にとっても有益な面がたくさんあります。
1. 成虫の活動と食性
成虫は主に日中に活動し、様々な種類の花を訪れて蜜や花粉を摂取します。キク科、セリ科、アブラナ科など、小さな花が集まった形状の花を好む傾向があります。花から花へと飛び回ることで、植物の受粉を助けるポリネーター(花粉媒介者)としての役割も担っています。
彼らの得意なホバリングは、花の蜜を効率よく吸うためだけでなく、天敵から逃れたり、縄張りを主張したり、配偶相手を探したりするためにも役立っています。風の強い日でも巧みにホバリングする姿は、まさに小さな飛行の名手と言えるでしょう。
2. 幼虫はアブラムシハンター!
ホソヒラタアブの生態で最も特筆すべきは、その幼虫の食性です。ホソヒラタアブの幼虫は、アブラムシ類(アリマキ)を専門に捕食する天敵として知られています。
- 産卵: 成虫のメスは、アブラムシのコロニー(集団)の近くを選んで産卵します。1匹のメスが生涯に産む卵の数は数百個にも及ぶことがあります。卵は乳白色で細長く、アブラムシが付着している植物の葉や茎に1個ずつ、あるいは数個まとめて産み付けられます。
- 幼虫の形態と捕食活動: 卵から孵化した幼虫は、脚のないウジ虫のような形をしています。体色は淡緑色や黄緑色で、半透明なため、捕食したアブラムシの体液で体色が変化することもあります。眼や脚はありませんが、頭部を左右に振りながらアブラムシを探し当て、鋭い口器で体液を吸います。1匹の幼虫が成長するまでに捕食するアブラムシの数は、数百匹から多い時には1000匹以上にもなると言われており、その捕食能力は非常に高いです。
- 農業における益虫としての役割: アブラムシは多くの農作物や園芸植物にとって大害虫です。植物の汁を吸って生育を阻害するだけでなく、植物ウイルス病を媒介することもあります。ホソヒラタアブの幼虫は、このアブラムシを効率的に捕食してくれるため、農薬の使用量を減らすことに貢献する「生物農薬」あるいは「土着天敵」として非常に重要な存在です。
3. ライフサイクル
ホソヒラタアブのライフサイクルは、卵、幼虫、蛹、成虫の完全変態です。
- 卵期: 数日程度。
- 幼虫期: 1~2週間程度。この間に数回脱皮を繰り返して成長します。
- 蛹期: 1週間~10日程度。成熟した幼虫は、葉の裏や茎などで蛹になります。蛹は涙滴型で、最初は緑色ですが、次第に褐色に変化します。
- 成虫期: 数週間程度。
気候条件にもよりますが、ホソヒラタアブは1年に数世代を繰り返すと考えられています。暖かい地域では、春から晩秋まで継続的に発生が見られます。越冬は、主に幼虫または蛹の形態で行われることが多いですが、温暖な地域では成虫で越冬することもあるようです。
ホソヒラタアブの仲間たち~似ているヒラタアブ~
ヒラタアブの仲間は種類が多く、ホソヒラタアブにもよく似た近縁種がいくつか存在します。代表的なものとしては、以下のような種が挙げられます。
- ナミホソヒラタアブ (Sphaerophoria philanthus): ホソヒラタアブによく似ていますが、腹部の黄色い帯の形状や、オスの腹端の形状などで区別されます。ホソヒラタアブよりもやや小型の傾向があります。
- フタホシヒラタアブ (Eupeodes corollae): やや太めの体型で、腹部の黄色い斑紋が途切れて一対の点のように見えることが多いです。
- ナミヒラタアブ (Syrphus ribesii): 最もよく見かけるヒラタアブの一つで、ホソヒラタアブよりも体型が太く、腹部の黄色い帯がはっきりしています。
これらの種を見分けるには、腹部の斑紋のパターンや、オスの交尾器の形状などを詳しく観察する必要がありますが、野外での正確な同定は難しい場合もあります。
ホソヒラタアブと私たちの関わり~益虫としての恩恵~
ホソヒラタアブは、私たち人間にとって多くの恩恵をもたらしてくれる益虫です。
- 農業・園芸の味方: 幼虫がアブラムシを大量に捕食してくれるため、農薬に頼らない害虫管理(IPM:総合的病害虫管理)において重要な役割を果たします。家庭菜園やガーデニングでも、アブラムシが発生した際にホソヒラタアブの幼虫を見かけたら、それは頼もしい助っ人が来てくれた証拠です。
- 花粉媒介: 成虫は花々を飛び回り、蜜や花粉を食べる際に花粉を運び、植物の受粉を助けます。これは、生態系の維持や農作物の結実にも貢献しています。
- 環境指標昆虫: ホソヒラタアブなどのハナアブ類は、多様な環境に生息し、環境の変化にも比較的敏感です。そのため、その地域の生物多様性や環境の状態を知るための一つの指標となることがあります。
ホソヒラタアブを観察してみよう!
ホソヒラタアブは、私たちの身近な環境で比較的簡単に見つけることができます。
- 観察ポイント: 日当たりの良い草地や、様々な花が咲いている場所、アブラムシが発生している植物の周りなどを探してみましょう。特に春から秋にかけての晴れた日には、活発に活動する姿を観察できるでしょう。
- 観察のコツ:
- ホバリングしている姿を見つけたら、そっと近づいてみましょう。驚かせなければ、しばらく同じ場所でホバリングを続けることがあります。
- アブラムシがたくさんついている植物の葉の裏などを丁寧に探すと、幼虫や蛹が見つかるかもしれません。
- 写真撮影に挑戦するのも面白いでしょう。ホバリング中の姿を捉えるのは少し難しいですが、花の蜜を吸っている時などは比較的撮影しやすいです。
【注意点】
ホソヒラタアブはハチに似ていますが、毒針は持っておらず、人を刺すことはありません。攻撃性もないので、安心して観察することができます。ただし、他の昆虫(特にハチ類)と間違えないように注意しましょう。
まとめ~小さなヒーロー、ホソヒラタアブを守ろう~
ホソヒラタアブは、その可愛らしい見た目だけでなく、アブラムシを捕食する益虫として、また花粉を媒介するポリネーターとして、私たちの生活や生態系に大きく貢献している重要な昆虫です。
近年、生息環境の悪化や農薬の使用などにより、このような益虫たちの数が減少していることが懸念されています。私たちの周りの自然環境に関心を持ち、農薬の使用を控えるなど、ホソヒラタアブをはじめとする小さな生き物たちが暮らしやすい環境を守っていくことが大切です。
次にホソヒラタアブを見かけたら、その小さな体で一生懸命に活動する姿を温かく見守り、彼らが果たしてくれている大きな役割に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。きっと、自然の奥深さや、小さな生き物たちとの共生の素晴らしさを再発見できるはずです。
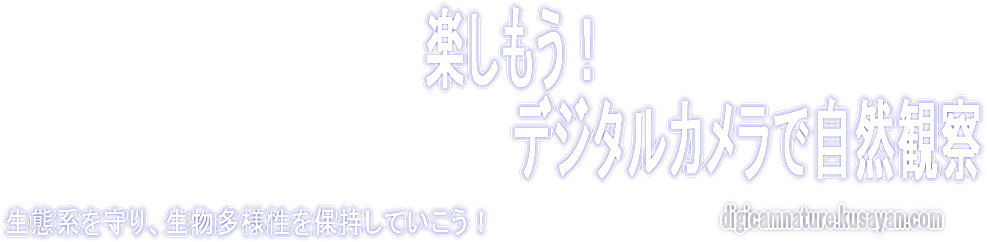


コメント